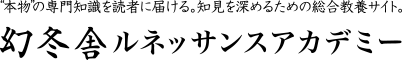連載
一覧科学を統治する市民を育てる【第4回】 クライアントシップの教育

荻原 彰(おぎはら あきら) 三重大学 教育学部
クライアントシップの教育 自動販売機モデルからの転換
東日本大震災の原発災害に際して、日本学術会議の当時の会長は“学者の意見はお互いに違って当然だが、外へ出ていくときには統一されていなくてはならない”と述べたという。日本気象学会でも、会員の研究者らに、大気中に拡散する放射性物質の影響を予測した研究成果の公表を自粛するよう求める通知を出していた。科学者から様々な異なる意見が世の中に出ていくときの混乱と科学者不信を恐れた対応であろう。これらの言論統制めいた考え方には科学者の市民不信の底流を感じることができる。
しかしこのような科学の指導者の態度を情報隠しと一方的に責めることはできない。市民やその意向を体現するメディアは専門家(以下、科学者だけではなく技術者や技術官僚など科学技術をバックグラウンドとする職業も含めるので専門家と呼ぶ)にすべての情報の公開を求める一方でそれらを縮約した「わかりやすい説明」を求める。専門家が様々な留保をつけて正確に説明しようとすると「要するに何なのか」といらだつ。調査や研究の進展に伴う説明の変転に「今まで言っていたことと違う」という不信感をぶつける。市民は専門家を、問いを入力すれば、唯一で確実な答えを市民に提供してくれる情報源、自動販売機のようなものとみなしている。専門家がユニークボイス(統一された見解)にこだわるのは市民のこのような考え方の反映という側面があるのである。
トランスサイエンス問題をテーマとする科学教育は、このような自動販売機モデルと対極のものでなくてはならない。では専門家と市民の関係をどのようなモデルでとらえればよいのだろうか。
かつて対人的専門職(典型的なのは医師と弁護士である)とその顧客(クライアント)の関係は、最善の決定は専門職がその専門性を駆使して行うことができるのであり、クライアントはそれに従えばよいという関係だった。専門職が権限も責任も独占していたのである。しかし現在、少なくとも理念の上では、専門職は助言を行い、顧客はそれらの助言を得たうえで、医療上・法律上の決断をして、それを専門職が実行するというように、クライアントと専門家は責任と権限を分有するようになった。
私は、科学技術の専門家と市民の関係もこのような関係性をモデルとすることができると考える。トランスサイエンス問題にかかわる意思決定は科学的判断というよりも社会的判断であり、それは専門家の助言を得たうえで、社会全体で、つまりは市民自身が決めることである。そこには権限とともに市民の責任が発生する。その責任をはたすための専門家との関係性(クライアントシップと言っておこう)が求められるのであり、そのための教育が必要となる。
私はクライアントシップの教育に必要な要素として次の3つを考えている。
1 科学の暫定性、学説の多様性を強みととらえる
科学は無謬ではない。無数の検証に耐えて生き残ってきたニュートン物理学などのようなきわめて頑健な理論もあるが、ほとんどの理論は暫定的であり、修正されていく。もっとあけすけに言えば、多くの場合間違うのである。トランスサイエンス問題のように複雑な条件が関係し、ローカルな文脈が重要になる問題では、なおさらのことである。しかし科学はそもそも先行研究を修正・否定することによって進歩していくものであり、科学の強みはむしろその修正可能性、現在の到達点をひとまずの足場とみなす暫定性にあることを市民は認識する必要がある。
もうひとつはこれらの足場(学説)の多様性である。地球温暖化や放射線の確率的影響の議論にみられるように、現在進行形の現象の解釈については、いくつかの学説が競合するのが普通である。つまり「人によって言うことが違う」。しかしこれは異常なことでも困ったことでもなく、科学にとってはこれが通常であり、違うからこそ学説間の淘汰と最適化が起こる。市民はこのような科学の本質を理解し、トランスサイエンス問題に対する答えの多様性、不一致を問題解決の障害ではなく、資源と考えることが必要である。
2 専門的見解の布置を知る
上に述べたようにトランスサイエンス問題に対する専門家の見解は異なるのが普通である。たとえば原子力の専門家の中にも原発の安全性について多様な見解があり得る。しかしここで注目したいのは、より広い範囲での専門家の見解、異なった学問間にみられる見解の多様性である。
津波と原発の例について見てみよう。9世紀に起こった貞観地震について、津波研究者は、津波堆積物の分布等から数値シミュレーションを行い。貞観地震が長さ200km、滑り量7mの巨大な断層運動によるものであって、近代記録に存在しない異種の巨大地震であること、近代記録に依拠した津波対策は不十分である可能性が高いこと、地震が1000年に1回程度の再来間隔であり、再来の危険性が高まっていることを東日本大震災の数年前には明らかにしていた(貞観津波が福島第一原発の脅威になりうること自体はすでに1990年ころから津波研究者は認識していた)。しかし原発の専門家はモデルの不確実性を理由に積極的な対策をとることに慎重であった。市民がこの事情を知ることはほとんどないまま、津波対策は先送りされ、2011年3月11日を迎えたのである。
このような場合、原発の専門家のみを専門家とし、その見解を教育の場に使用することは当を得ていないことはあきらかだろう。しかしエネルギー教育の資料として文科省と経産省が2010年に共同で作成した『チャレンジ原子力ワールド』には、“大きな津波が遠くからおそってきたとしても、発電所の機能がそこなわれないよう設計しています。さらに、これらの設計は「想定されることよりもさらに十分な余裕を持つ」ようになされています”と原発の専門家の見解のみが記されている(この資料は東日本大震災後回収された)。
専門家の見解の多様性は自然科学の内部にとどまらない幅をもっている。現在頓挫している核燃料サイクルについて、原発の専門家はプルトニウム抽出・輸送等の個別技術について安全性が確保されているとしているが、テロ抑止のため日本が警察国家になりうる危険性を警告する社会科学の専門家も存在する。各個別技術の安全性に着目するフレーミング(問いの枠組み)と社会はどう変わるのかというフレーミングの違いである。個別技術は独立に社会に取り入れられるわけではなく、システムとして取り入れられるのだから、そのシステムが社会をどう変えるかという社会科学・人文科学の視点も当然必要になってくる。
このようにトランスサイエンス問題には多様な分野の専門家がかかわりを持つのであり、それらが相互に矛盾することも稀ではない。市民がトランスサイエンス問題を適切に理解するためには、それらの矛盾点、対立点も含めどのような見解が存在し、それらが相互にどのような関係があるのか、つまり諸見解の布置を把握しなければならない。
教育者の側から言えば、学習者が理解しやすくするため、諸見解を一覧し、整理してわかりやすく配列(マッピング)する作業が必要になる。これは容易な作業ではない。しかし科学教育や科学コミュニケーション論にとっての豊饒なフィールドがここに存在することも確かである。科学教育の発展の方向性の主要なもののひとつであると筆者は考える。
3 専門的見解の布置をタネとして自分(たち)のとるべき選択肢を話し合う(熟議)
専門的見解の布置が一覧できれば、自分(たち)がその中から選ぶべき選択肢を考えるタネとしてその布置を活用する。つまりトランスサイエンス問題に対して社会がどのような道を選択すべきか考え、話し合うのが次の段階である。この話し合いは主として授業の中で行われるが、話し合いの参加者は児童生徒に限定されない。むしろ専門家や地域の人々を交えて議論するのが望ましい。ICTを利用すれば条件の違う複数の学校(たとえば原発立地地域の学校と都市の学校)が参加する討議も可能になる。また希望者にはなるだろうが、地域での集会や公聴会に参加することも奨励される。この段階で大切になってくることを列挙すると次のようになるだろう。
(1) 差異は資源である
学校理科で扱う科学的知識は多くの場合、その結論(着地点)が決まっており、当初意見の差異があっても最終的にはそこに向けて着地しなければならない。児童生徒が異なった結論に着地してしまったら、教師は大慌てで「本当はね・・」と修正する。しかしトランスサイエンス問題の場合、着地点は決まっていないし、学習者によって着地点が異なっても構わない。
近くの川の治水手法を扱う場合、水害の経験をもとに巨大なコンクリート堤防を求める者、魚取りの経験をもとに近自然工法を求める者、祖父の経験をもとに昔あった遊水地の復活の可能性を主張する者(地域固有の知の持ち込み)など意見とその根拠が多様であればあるほど話し合いは豊かになる。話し合いを進める中で、それぞれの意見の背後にある価値観、時には主張する本人ですら気づいていなかった価値観があらわになり、価値観の相互理解(賛同という意味ではない)が進んでいく。最終的に各自がどのような結論に着地するかということよりも、このようなプロセスの豊かさ、このプロセスを経ることによって学習者の考え方の幅が広がることがより重要である。この意味で差異は資源である。
(2) 公正に配慮する
トランスサイエンス問題によって発生するリスクは社会内で不平等に配分されることが多い。たとえば福島第一原発事故の際、原発の恩恵をもっとも受けていた東京の人々は大きな被害を受けなかったが、原発の電気を1wたりとも使っていなかった周辺地域の人々が故郷を追われ、生業を喪失した。なぜ東京電力が福島や新潟に原発を作ったのかといえば、「東京のそばにこんなあぶないものを置いておけない」という論理が暗々裏にあったことはあきらかである。
国外に目を向ければ、ウラン燃料の安いコストの背景には、深刻な被爆を受けながらもそこで働かざるをえないカナダ先住民やアフリカの人々がいる。トランスサイエンス問題にかかわるこのような不平等(というよりも不公正といったほうがいいだろう)を考慮しない議論は、リスクを強制する側の責任を無化し、自己の立場を代表できない人々(社会的経済的弱者や子ども)、さらには動物などの自然の犠牲を、一般的なメリット・デメリットの議論の中にまぎれこませて正当化しかねない危うさを持つ。指導者は、議論の前提として、不平等・不公正が存在する場合、それを明示的に指摘して考慮するように求めることが必要である。
(3) 市民参加の方略に踏みこむ
トランスサイエンス問題を扱う教育の究極の目的は、市民が専門家とともに科学技術やそれにかかわる政策の方向性を決める、つまり市民による科学技術の統治である。したがって、教育を通じて学習者が、あるトランスサイエンス問題について自分の立場を決めていくことは、トランスサイエンス問題を扱う教育の重要な要素ではあるが、ゴールではない。市民が科学技術の統治をおこなうことができるための具体的な方略、どうすれば市民が科学技術の方向性に対して実効的に関与できるのかという側面に踏み込む必要がある。
これは公衆や政策決定の権限を持つ人々への主張の伝達や対話、投票や裁判を通じた意思表示といった、市民が影響力を行使する多様な回路を知る、場合によっては実践するということであり、市民性教育の一環として考えることができる。ただこれは社会科で行われるような制度についての知識を中心としたものではない方がよいだろう。制度についての知識もある程度必要ではあるが、それが中心となると、客観的ではあるが、何かよそよそしい知となりがちである。
それよりも、これまでのトランスサイエンス問題にかかわる市民運動の中での人々の思いや行動を、語り、手記、ジャーナリストの記録などを通して、内側からなぞり理解するという手法がより効果的であるように思われる。市民が行動に踏み出すには思いが必要であり、その思いへの理解なしでは行動の意義を腑に落ちて理解するのは難しいからである。