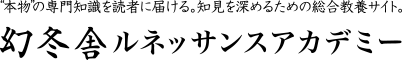連載
一覧科学を統治する市民を育てる【第3回】 フレーミングの吟味と選択

荻原 彰(おぎはら あきら) 三重大学 教育学部
問いが違えば答えが変わる―フレーミングの吟味と選択―
先のブログで「トランスサイエンス問題を考え、判断することのできる市民を育成する」ことが初等中等教育における科学教育の重要な使命であることを述べたが、では具体的にトランスサイエンス問題をどう扱えばよいのだろうか。
「トランスサイエンス問題を考え、判断することのできる市民を育成する」ことは、現在の初等中等教育における科学教育の内容の大部分を占めている、「専門教育の基礎となる科学知識やスキルの体系的学習」と内容的には重なる部分も多いが、基本的に別物と考えたほうがよい。その理由は2つある。
一つの理由は、トランスサイエンス問題への理解を阻む専門的知識の壁である。トランスサイエンス問題は多くの場合、先端科学技術、たとえば遺伝子組み換え、原子力発電といった科学技術と社会の境界面に発生する。問題に直接関連する専門家でないと詳細にそして正確に理解することは難しい。もちろん、だからと言って専門家に白紙委任というわけにはいかない。専門家の理解のような基礎からの体系的理解ではないが、問題の要点はしっかり把握するというタイプの理解が必要であり、これは「専門教育の基礎となる科学知識やスキルの体系的学習」という、現在の科学教育の目指す理解の方向性とは異なる。たとえて言えば優秀な政治家や官僚の科学技術理解に近いものであろう。ただここではこの問題にこれ以上言及せず、もう一つの理由、フレーミングの問題に話題の焦点を絞りたいと思う。
フレーミングとは枠づけ、つまり事象を切り取る問いの枠組みをさす。同じ事象であってもフレーミングが異なれば答えは異なる。アメリカの市民や政治家は第2次大戦を「正義はどちらにあったのか(アメリカなのか、日本やドイツなのか)」という枠組みで問うことが多い。国家を主体とした問いである。その答えは「正義はアメリカにあった」であろう。一方、広島・長崎の市民は「なぜあのような理不尽な死が私の家族や友人にもたらされたのか」と問うだろう。戦争で死んだり傷つけられていく一人一人の個人を主体とした問いである。この問いに答えることは難しいが、一つの答えは原爆慰霊碑に刻まれている「安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから」であろう。原爆はどのような理由があろうとも使ってはならなかったものであり、原爆投下は端的に過ちであったのだ。2つの問いに優劣の差はないが、スミソニアン博物館での原爆被害の展示拒否の議論が示すように、フレーミングの違いは対話の成立を阻み、ときにはとめどのない対立をもたらす。
読者の皆さんは、科学は、誰もが認めざるを得ない客観的知識を構築する営みであり、立場の違いを超えていくものと認識されておられるかもしれない。確かに、たとえば運動方程式は世の中のどこにでも通用する。窓から飛び出せば右派であろうと左派であろうと、9.8m/s2の加速度で落ちていく。
しかし、科学が社会と接点を持ち、科学技術となっていき、さらにそれがトランスサイエンス問題となって社会の中に組み込まれてくるとフレーミングの違いが顕在化してくる。
遺伝子組み換え作物の例をあげてみよう。「ある遺伝子組み換え作物Aは安全か」という問いでフレーミングを行う場合、医学や栄養学の視点から見る人は、「ヒトへの健康影響」を問題とするだろう。しかし「ヒトにとってある遺伝子組み換え作物Aが安全である」という結果が確定したとしても、生態学者や自然保護に携わる人は「生態系にとって遺伝子組み換え作物Aは安全か(遺伝子汚染が広がらないのか)」という独立した別個の問い(フレーミング)を立てるだろう。農家にとっては「農業経営に対して遺伝子組み換え作物Aが安全か」という問いも重要となる。遺伝子組み換え作物によって安定した高収量が確保されたとしても、遺伝子組み換え作物の種子を供給する企業に種子を全面的に依存すると品種の多様性が損なわれ、災害や想定していなかった病害に対して脆弱になる可能性はあるからである。
さらに農薬を使う在来農業と使わない有機農業の間でもフレーミングとその答えは異なる。在来農業の農家の場合、たとえば害虫抵抗性のある遺伝子組み換え作物は当該害虫に対する殺虫剤散布の必要がなく、殺虫剤の環境影響や農家の労力の削減に役立つので農業経営への福音と歓迎されるかもしれない。しかし有機農業の農家の場合、そもそも殺虫剤を使わないし、このような作物の遺伝子が、自分の栽培している作物の遺伝子に紛れ込むと、有機農業としての認証や消費者の支持を得られなくなる可能性がある。平川秀幸によれば、実際、EUではこのような論争があり、「環境NGOやオーストリア・デンマーク政府などは、工業的農法を自明の前提にした欧州委員会の評価は不完全であり、農薬を使わない有機農法も視野に入れた基準にすべきだと主張した。その根底にあったのは、環境負荷の少ない有機農法や工業的な大規模農業の広がりによって駆逐されつつある地域固有の食材や食文化を護り、広げていくべきだという食と農の未来ビジョンであり、それを望ましいとする価値の選択だった。」という。
つまり「ある遺伝子組み換え作物Aは安全か」という、一見すると科学的事実に関する客観的判断の問題に見えるものであっても、議論が広がっていけば、価値観や文化の判断をふくみこんでくるのである。
このような問題(これは先に論じたトランスサイエンス問題にあたる)を理解する場合、科学知識やスキルの体系的学習では不十分であることは明らかであろう。むしろ必要なのは、価値観や文化を背景として持つ多様なフレーミングがありうることの理解(これは一種の多文化主義といえる)、それらのフレーミングのよって立つ論理を吟味し、その論理を受け入れるのか受け入れないかを決めること(批判的吟味)、そして自分(たち)自身がもっとも重視するフレーミングを選択することである。この場合、重要なのは議論の素材となる科学知識やスキルよりも、むしろそれを解釈する多様なフレーミングの論理の理解と選択になる。
現在の科学教育でもトランスサイエンス問題を扱うことはある。しかしそれは多くの場合、科学知識やスキルを獲得したうえで、それらの応用問題として扱うのである。私は上に述べた観点から考え、トランスサイエンス問題を扱う教育において肝要なのは科学知識やスキルではなく多様なフレーミングの理解と選択だと主張したい(むろん自然観察などトランスサイエンス問題と直接かかわらない領域はこの議論の対象とはしていない)。このプロセスの中でトランスサイエンス問題にかかわる科学知識やスキルを理解するのであって知識やスキルの獲得自体を目的とはしない。つまり現在の科学教育とは入り口と出口が逆転する。たとえてみれば原発立地地域でやむにやまれず原発について学習する住民の学習と相似形の学習である。このような科学教育の転換は冒険ではあろう。しかし獲得された知識が「生きてはたらく知識」となることは間違いない。価値ある冒険となることを確信している。