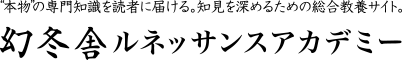連載
一覧夏目漱石の予言 【第1回】―文芸の可能性 ―

半藤 英明(はんどう ひであき) 熊本県立大学 学長
作家の創造物を文芸、そして、学問の対象としてのそれらを文学と呼ぶとしよう。文芸が社会を映し出す鑑であると言うつもりは毛頭ないが、文芸と社会が強く連関しており、社会が文芸を育てることは事実である。司馬遼太郎は、明治維新を「文化大革命」と評した(中公文庫『日本語と日本人』)が、明治期の文芸は濃淡の差こそあれ、社会的な革命の時代に応じ、ぜひとも筆を執らずにはいられなかった者たちの内面すなわち思想や主張や美意識や試行錯誤や喜怒哀楽の感情から形づくられた時代精神である。人が社会的な存在であり、社会のなかで育まれる以上、人生とは原理的に社会の影響を受ける。
文芸が語れる社会は人ひとり一つの物差しで規定できるものではないという判断からだろう、近年は集団の幻想を映し出す文芸がほぼ見られなくなった。文芸を発信したい人も受容したい人も共感したい人もいるが、文芸の生命は個人に帰属すると思われていよう。文芸に対し、社会を動かす力を期待する向きはない。それでこそ文芸であるということもあろうが、なれば、文芸は個人的な趣味や慰みに向かうのみである。しかし、人が社会的な存在であるように、文芸を社会的な存在と決めつけるならば、人と同じように文芸にも可能性が拡がり、文芸の価値を紐解く「文学」には当然の使命が生ずる。ここに、文学の使命を再確認するに当たり、文芸の可能性に人生を賭けた者たちのなかから夏目漱石の声を復元したい。
「継続は力なり」の教訓は漱石にも当てはまる。吉本隆明は、漱石を評して「漱石でまず驚くのは、初めの『吾が輩は猫である』から最後の『明暗』の途中で亡くなるまで、一度も停滞していないことだ。たるみの時期がない。」と述べる(新潮文庫『日本近代文学の名作』)。小説を恒常的に発表する難しさは、作家の力量と苦悩を慮ることである。英語教師としての煩事よりも専業作家としての苦悩を選んだ漱石であるが、一度も停滞せずに小説を発表し続けることができたのは、漱石の批評精神が結果として人生の本質に向かっていたからではなかったかと考えている。