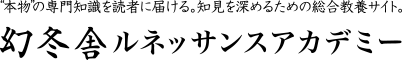連載
一覧韓国における元徴用工裁判と日本の対抗的措置【第4回/完】ー 日韓の解釈の対立、国際法と国内法の関係
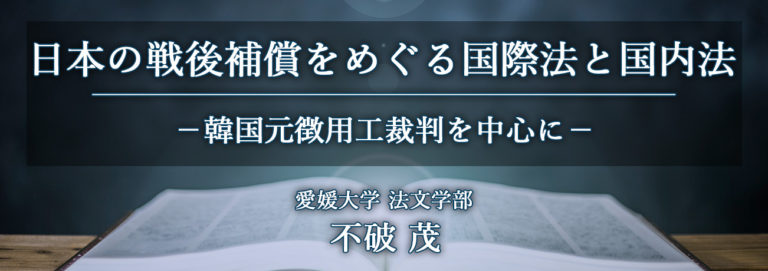
不破 茂(ふわ しげる) 愛媛大学 法文学部
1.韓国大法院判決
サンフランシスコ平和条約4条(a)により、韓国等との特別取り極めの対象とされたのは、次の財産及び請求権である(*i)。
①日本国及びその国民の財産で朝鮮半島にあるもの、日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で、朝鮮半島を実効支配する政府[この後韓国と表記する(筆者注)]、及びその住民(法人を含む。)に対するものの処理、
②日本国における韓国及びその住民の財産、日本国及びその国民に対する韓国及びその住民の請求権(債権を含む。)の処理
これに基づき、日韓請求権協定が締結されたのである。
同協定2条1項が、日韓両国及びその国民(法人を含む。)の「財産、権利及び利益」並びに、両国及びその国民の間の「請求権」に関する問題が、サンフランシスコ「平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて[下線筆者]、完全かつ最終的に解決された」と規定している。そして、同条3項が、相互の締約国の管轄下にある相手国及びその国民の「財産、権利及び利益」に対する措置、及び締約国及びその国民相互間の「すべての請求権」に関しては、「いかなる主張もすることができない」としている。
この「財産、権利及び利益」、「請求権」、及び「いかなる主張もすることができない」という文言の意味について、日本と韓国の間に解釈の相違を生じている。日本の政府及び裁判所の解釈については前回、述べた。
サンフランシスコ平和条約は、戦争当事国である日本と連合国側との間の、戦争賠償や財産的処理について規定するものである。韓国は日韓併合以来日本の統治下にあり、第二次世界大戦中、朝鮮半島は大日本帝国領域の一部であった。朝鮮半島の住民がその臣民とされていたのである。軍事力を背景としたそのような植民地支配が今日の国際法上は違法であることに疑いがない。そうであるとしても、韓国は、戦勝国及び戦敗国という平和条約の当事国たり得ない。しかし、韓国は戦争賠償に与ることはできず、従ってその放棄とも無関係であるが、違法な植民地支配に基づく賠償を求めることは可能であるというのが韓国の立場である。韓国の裁判所によると、日本の植民地支配に対する賠償と、第二次世界大戦終了時における日韓の財政的・民事的な債権・債務関係を区別している。(*ii)
新日鉄事件大法院判決に曰く、日韓請求権協定は、サンフランシスコ平和条約4条(a)に基づき財政的民事的な債権債務関係を政治的合意によって解決するためのものである。前回触れた韓国側が提示した財産及び請求権協定要綱8項目も財政的民事的債務関係に関するものであり、元徴用工の未払い賃金及び補償金というのも、その趣旨に限定される。その事件において求められているのは、「不法な植民地支配および侵略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為」であり、強制労働による精神的苦痛に基づく慰謝料請求は、財政的民事的債務とは区別されるとしている。
これが、大法院判決の多数意見である。大法院の裁判官13人中、2人の反対意見がある。わが国の西松建設最高裁判決とほぼ同様の理由付けにより、多数意見の結論に反対している。更に、3人の補充意見は、徴用工の損害賠償請求が請求権協定に含まれているとする。しかし、「完全かつ最終的に解決された」という文言を外交保護権のみを放棄したという意味に解している。従って、徴用工請求権が日韓請求権協定に含まれているか否かの点では、大法院裁判官の立場が、8対5に分かれていることになる。
サンフランシスコ平和条約4条(a)にいう「財産」の原文はpropertyであり、「請求権(債権を含む。)」は、claims, including debts である。平和条約4条に基づき締結された日韓請求権協定が明文で規定するように、平和条約4条(a)を包括するのである。要綱8項目にいう「補償」の語にしても、各々極めて一般的で包括的な用語であるが、韓国大法院判決は、先に述べたようにこれを狭い意味に限定解釈している。
条約は、文言の通常の意味に従い、当事国の関係合意等に基づき解釈しなければならず、補充的にその他の交渉記録や締結時の事情を考慮して解釈される。大法院判決は一般的、包括的な用語を、目的的に限定解釈しているのである。特に二国間条約は法であるとしても、契約に類比されるように、当事国間の法であり、締結時の合意内容に拘束される必要がある。日韓請求権協定締結後の韓国国内の立法措置等が、条約解釈に関わる韓国の国家実行を示すとすると、韓国の立場が2005年を境に大きく変更された。当事国が条約の解釈を、一方的、恣意的に変更することは許されない。
確かに、日韓併合が合法か違法かについては、日韓請求権協定の締結時には合意に至らなかった。しかし、この点を棚上げして、日本が韓国に対して「経済援助」を行うことで、韓国も手を打ったのである。サンフランシスコ平和条約を受けて、戦争賠償および請求権に代わる、植民地支配に基づく賠償および請求権が、日韓請求権協定に含まれているとする方がより率直である。一括処理方式によったという理解である。連合国はこれを放棄したのであるが、韓国は放棄せず、格別の経済援助を受けつつ、これ以降、互いに「主張し得ない」という方途を選択したのである。後になって、請求権協定に明示的に言及されていないのだから、植民地支配に由来する個人請求権については、実体権としても、外交保護権としても失われていないというのは不意打ちとも言える。
2018年大法院判決も、日韓請求権協定の解釈に際して、国際慣習法である条約解釈の手順に従っているのではあるが、従って、強弁の感を免れない。その理由をもう少し考えてみよう。
2.日韓請求権協定と韓国憲法
日本は、請求権協定の交渉において、日韓併合が当時の国際法上は合法であるとし、元徴用工の強制労働に基づく賠償を否定していた。確かに、第二次世界大戦の以前、国際社会は西欧諸国を中心とする列強により分割され、多くの植民地支配が存在した。日本はそのような国際的傾向の中で、朝鮮半島に、軍事的脅威を背景として進出したのである。日韓請求権協定は、この問題を棚上げしたまま締結された政治的、法的な合意である。
第二次世界大戦中、植民地である朝鮮半島の出身者は、日本の国民とされたので、戦時下の徴用にしても、当時妥当していた法に基づき、他の日本国民と法的には同列であった。このころ、炭鉱労働や土木作業などの労働現場が過酷な労働環境にあったことは、出身が内地であっても、朝鮮半島であっても、恐らくいずれにしても異ならないであろう。この点で、外国による侵略を受け、他国に強制連行ないし欺罔されて応募した者が、過酷な労働条件や反人道的扱いを受けたと言うか、戦時下、戦争当事国の国民が同様の扱いを受けたと言うかの相違があるのみである。韓国側は韓国の立場が前者であることを強く主張し、その賠償を当然視している。元徴用工に対する補償について、韓国内において、既に、国による一定の給付が存在するようである。これが不十分であるとして、韓国内で言うところの「戦犯企業」に対する賠償を可能としたのである。
韓国における国際法と国内法の関係についての解釈がどのようなものであるかを、筆者は知らない。しかし、日本の憲法学説の通説および行政解釈におけるような国内法優位の一元論を前提すると、条約たる国際法も、韓国国内においては韓国憲法に反することはできない。そのような条約は無効とされる。
2012年5月24日の大法院判決は、新日鉄事件において、反対の原審を破棄、差戻した判決である(*3)。同判決が韓国憲法を引用している。韓国制憲憲法および現行憲法前文において、日本の植民地支配に対する抵抗運動である1919年の3・1運動後、中国に樹立された臨時政府の法統と、戦後、1960年の、李承晩政権に対する民主化運動である4・19革命の理念を継承するとしている。現在の韓国政府は、日本の支配に抵抗した独立運動の主体である亡命政権を継承したとしているのである。同判決によると、この憲法の精神の下、日韓併合条約は違法であるとする。これが、韓国憲法を頂点とする韓国国内法秩序である。
韓国の憲法に反する国際法は無効とせざるを得ないので、大法院判決は、日韓請求権協定を韓国憲法に反しないように限定解釈したと考えることができるかもしれない。いずれにせよ、韓国国内法上は、これらの大法院判決により、日韓請求権協定の解釈が最終的に確定されたのである。(*ⅳ)
以上は法解釈としての立場である。韓国政治の専門家ではないが、次の点を指摘しておきたい。韓国の裁判所がときの政権におもねる判断を下すことがあるとされている。日本であれば、政治問題であり、判断を回避するとする場面でも、むしろ積極的に政府の思惑を忖度するような判断を下すことがあるのかもしれない。日本の安倍首相が日本の戦後を総決算すると言うならば、韓国の文大統領は、第二次世界大戦後、日本が朝鮮半島に遺したものを精算すると言うのである。これが政治的な反日の徹底である。結果的に日本の人的、物的な遺産を利用した李承晩政権と、日本の経済援助を用いた朴正熙政権による経済発展の歴史に対して否定的な態度を取る。今日の保守系の系譜に連なるからである。日本の遺産を一掃するという反日の運動が文政権の基盤を形成する。日韓請求権協定は、李承晩時代に交渉が開始され、朴正熙政権によって決定された、戦後の日韓関係の枠組みの一つである。日韓請求権協定を巡る争いが、韓国国内政治において利用されている側面を感じさせる。
3.国内法と国際法の関係と対抗措置-再論
国内法と国際法の関係についての学説は、一元論と二元論に分かれる。更に、一元論には、国内法優位の一元論と、国際法優位の一元論が存在する。わが国の憲法学説および行政解釈が国内法優位の一元論によっている。国際法優位の一元論によるとすると、国際法に反する国内法が無効とされ、条約を締結、批准することで、憲法の改訂が可能となるからである。厳密な憲法改正手続が存在するにもかかわらず、この結論は背理である。国際法優位の一元論は、国際法学説における有力説であるが、多数説は、二元論によっている。二元論は、国際的場においては国際法が、国内的場においては国内法が、それぞれ至高の存在であり、いずれが優位に立つとも言えないとする。国際法に違反する行為であるとしても、その国の国内法上は完全に合法であり、自動的に無効とされるわけではない。二元論が、国際社会の現実に即していると思われるので、筆者もこの学説に与する。
日韓請求権協定という国際法について言えば、日本および韓国の解釈が対立している。日本からは、韓国の裁判所の判決および行政府がこれを容認していることが、国際法違反である。判決の強制執行手続が開始され、既に、日本企業の資産が差押えられている。手続上は、競売を経て換価されることになる。韓国国内において、自動的にこの判決が無効とされることは無いであろう。
国内裁判所と同様の意味においてこの争いを裁定する国際的な裁判所は存在しない。国際司法裁判所は、いわば仲裁に近いものであり、基本的に、当事国双方がその管轄に服するとして合意するのでなければ審理が始まらない。
国際法を巡る紛争を生じた場合に、相手国の国際法違反に対抗する対抗措置が一般国際法上認められる余地がある。国際法違反に対する国際法違反措置による対抗である。この問題点は、相手国の国際法違反の認定が一国の一方的な認定によるということである。WTO 上の対抗措置であれば、WTO法を解釈適用して裁定を下す中立的な機関が存在し、WTO法違反が認定されると、相手国に対する制裁としての対抗措置がWTOにより認められるのである。しかし、日韓請求権協定のような二国間条約の場合、このような中立的な裁判機関が存在ない。相互に相手国の行為が国際法違反であるとして、報復合戦、対抗措置の応酬に陥る恐れがある。結果的に、法ではなく、政治力、経済力ないし軍事力の大きな国に有利になりかねない。それでは、国際社会における法の支配に悖る。従って、対抗措置の発動自体、その国際法上の要件を具備することを、十分慎重に確認する必要がある。
条約の解釈について争いを生じた場合に、その解決方法が条約自体に規定されることもある。日韓請求権協定によると、当事国間における協議により解決することを原則としつつ、それでも解決しない場合に、国際仲裁によることが規定されている。しかし、これも、仲裁人選定等、その手続開始のために必要な当事国間の合意がなければ始まらない。実際に、日本が韓国に対して、仲裁の開始を通知したのであるが、韓国がこれを無視していた。
「大韓民国による日韓請求権協定に基づく仲裁に応じる義務の不履行について」と題する外務大臣談話が昨年公表されている。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_005119.html)
この第6項が、「昨年の一連の韓国大法院判決並びに関連の判決及び手続による日韓請求権協定違反に加え,今般,同協定上の紛争解決手続である仲裁に応じなかったことは,韓国によって更なる協定違反が行われたことを意味します」としており、第7項には、「日本政府としては,こうした状況を含め,韓国側によって引き起こされた厳しい日韓関係の現状に鑑み,韓国に対し,必要な措置を講じていく考えです」とされている。
日本政府は明言していないが、韓国に対する輸出管理規制の厳密化が対抗措置であるとも考え得る。条約上の紛争解決手続に、相手国が全く応じないというようなとき、この場合、具体的には国際仲裁に応じないというときに、相手国を中立的手続に服させるために、国際法上の対抗措置が可能であると解する(*ⅴ)。第2回で述べたように、現在継続中の対韓輸出管理の厳格化が対抗措置であるかには疑問も有り得る。今後、大法院判決に従った強制執行手続が進行し、日本企業の差し押さえられた資産の売却がなされたなら、更なる対抗措置が行われる余地があろう。
強制労働が禁止され、これに基づく民事的請求も認められなければならないというのが、国際法の現代的発展である。第二次世界大戦中、合法か、違法かは一先ず置くとしても、朝鮮半島は日本の植民地とされていた。徴用が強制連行により始まったか、あるいは欺罔に基づくとしても募集に応じたのであるか。いずれにせよ警察等の権力機関による監視下において、劣悪な労働条件の下で働かされたことが、強制労働にあたる。このことに対しては、今日の国際社会において、かつてより一層厳しい目を向けられることは確かである。
戦争犯罪人や国際人道法上の罪を犯した者に対して、国際的な犯罪として断罪し、かつ被害者に民事的救済を与えるべきであるとする、国際人権法および国際人道法の今日的発展も顧みる必要がある。しかし、第二次世界大戦中その事業主体となった日本の企業が、当時の国際社会において、厳密な意味で国際法上の犯罪人に当たるかについては、更なる検討が必要である。戦後補償のあり方について、日本とドイツを比較し、日本のそれが見劣りするとして批判する見解もみられる。しかし、ドイツのホロコーストが、ユダヤ人およびポーランド人に対する民族殲滅を企図した、非人道的な強制収容と大量虐殺であった。元徴用工裁判で問題とされる日本および企業の行為とは質的に異なる。しかも、ドイツにしても、一括処理方式の恩恵を受けたのであるが、これを否定するような個人請求は認めていない。
また、被害者に対する民事的賠償を認めることが、仮に国際慣習法として確立されているとしても、具体的な国内裁判において個人請求の直接的根拠となるとは理解されていない。韓国の大法院判決もこのような国際法に言及していない。国がその賠償を認める法制度や措置を講じる必要があるというに留まる。そして、民事的救済の方法として、具体的な民事訴訟の形で賠償を与えるべきであるか、あるいは国家的事業として金銭的給付を行うかといった財産的な被害塡補の方法が、厳密に規定されているわけではない。
この観点からは、日韓請求権協定の交渉および締結の経緯に鑑みれば、元徴用工に対する肉体的精神的な苦痛に対する補償は、まず第一次的には韓国政府がその責任を負うと解される。日本が何も負担していないというのではなく、多額の経済援助の形で支払っているのである。大法院判決によると、韓国政府も一定の給付を行っている。実際に被った損害に対する完全賠償の観点からすれば、不十分であるとして、その不足分の賠償を日本の企業に求めているのである。このような国家事業としての補償は、その財政的配分の観点からも、社会保障的な給付に留まるのであろう。完全な賠償が困難な場合に取られるような国家による補償のための措置を既に受けているとも言える。その上、賠償を請求する国際法的権利がなお存在するかについても疑問の余地がある。
元徴用工である原告は、過酷な労働環境に置かれた苦痛を認めて謝罪することも求めている。日本と韓国の間の、請求権協定を巡る紛争は、改めて両政府間において協議が開始されている。日本は、場合によっては、国際社会における法の支配の観点から、躊躇なく、対抗立法や更なる対抗措置を発動することも必要となる。しかし、少なくとも理念としては国際人道法上の要請も踏まえながら、政治的な和解に向けて努力もなされるべきである。
注
*ⅰ) わが国外務省の公定訳に基づく。
*ⅱ) 韓国の大法院2018年10月30日判決。日本の弁護士による次の仮訳を参照。http://justice.skr.jp/index.html 以下、新日鉄事件。
*ⅲ)判決の仮訳。日弁連「戦後補償のための日韓共同資料室」より。https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/sengohosho/saibanrei_04_2.pdf
*ⅳ) 参照、篠田英朗「日韓関係と「法の支配」-多元的な法規範体系における調整理論の必要性」論究ジュリスト30号75頁以下。篠田説は、この問題についての国際法優位の一元論的説明であると思われる。
*ⅴ) 連載第2回参照。