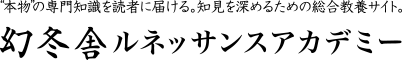連載
一覧韓国における元徴用工裁判と日本の対抗的措置【第3回】ー 日韓請求権協定について、わが国の法と判例
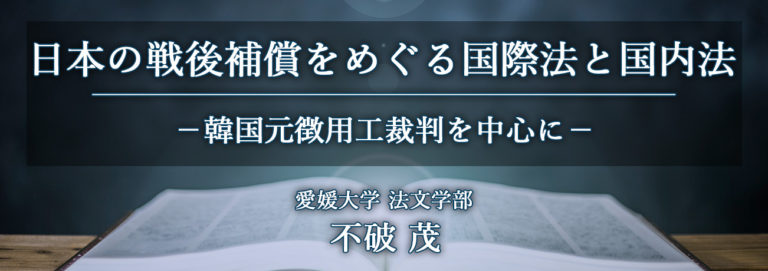
不破 茂(ふわ しげる) 愛媛大学 法文学部
日韓請求権協定が、日本及び韓国の二国間条約として、双方の国を法的に拘束している。戦後処理に係る請求権の扱いについて、双方の国の解釈が対立している。その前提となるのが、サンフランシスコ平和条約である。昭和27年(1952年)4月28日に発効した。昭和20年8月15日の終戦から、連合国軍により占領されていた6年を経て、このとき日本は主権を回復した。戦争賠償ないし請求権、及び戦争当事国領域内に残された財産の処理について、サンフランシスコ平和条約「第五章 請求権及び財産」において規定されている。日韓請求権協定に関するわが国裁判例を理解するために、まず、サンフランシスコ平和条約の該当規定について解説する。その後、西松建設最高裁判決を取り上げる。元徴用工である中国人被害者個人の、雇用主であった企業に対する損害賠償が争われた西松建設最高裁判決が、中国との関係において請求権放棄の意味を確定させたのである。最後に、日韓請求権協定における「請求権放棄」の意味に関するわが国の裁判例をみる。
1.サンフランシスコ平和条約
まず、日本が「戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して」、損害賠償を行う義務を有することが確認されている。しかし、同時に、直ちに完全な賠償を行うとすると、日本が存立可能な経済を維持できないこととなるので、以下のように合意するとされる(14条)。
すなわち、日本及び日本国民等が連合国の領域内に有した財産や権利等については、その連合国が差押えその他の処分を行う(14条(a))。同時に、連合国は、連合国のすべての賠償請求権を放棄し、更に、連合国は「戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権」を放棄する(同条(b))。
日本及び日本国民・企業が連合国に残した財産等を賠償に充当し、その代わり、連合国は日本に対する損害の賠償請求権を放棄するのである。更に、日本は、19条で、「戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた」、連合国及びその国民に対する、日本及び日本国民の請求権を放棄している。
第一次世界大戦の結果、敗戦国ドイツが過大な戦争賠償を負わされ、その債務返済に窮し、経済的に破綻したのであった。そのことが結果的に第二次世界大戦を招いたとの教訓から、敗戦国が持続可能な経済状態を維持できるように、過度の賠償を避けたのである。そして、国及び国民の個々の債務を積算して精算するのではなく、いわゆる一括処理方式によった(*ⅰ)。
なお、中国は、中華人民共和国と中華民国に分裂し、いずれも中国全体を代表すると主張していたため、どちらもサンフランシスコ講和会議に招かれず、サンフランシスコ平和条約の締約国とはなっていない。しかし、条約14条(a)の権利を有するものとされている(21条)(義和団事件後の処理に係る日本に認められた権益の放棄も規定されている(10条))。
同条約により、日本は、朝鮮の独立を承認した。同様に、台湾に対する全ての権利を放棄した。(2条)そして、日本にある、朝鮮・台湾の政府及び住民の財産の処理と、日本国及び国民に対する、朝鮮・台湾の政府及び住民の請求権の問題について、条約では棚上げされている。これらの地域を実効支配する政府及び住民に対する、日本国及び国民の請求権の問題を含めて、後に特別に取り決められることとされたのである(4条(a))。従って、朝鮮及び台湾についての戦争賠償や請求権について、サンフランシスコ平和条約では特別の規定が存在しない(*ⅱ)。
そこで、朝鮮との関係において、日韓基本条約と日韓請求権協定が締結され、中国との関係において、日華平和条約及び日中共同声明が締結ないし合意されたのである。中国については、中華人民共和国政府と中華民国政府が、中国全土における正統な政府であると主張し、対立していたのであるが、当初、日本は台湾を実効支配する中華民国のみを国家承認していた。そこで、平和条約としても、台湾政府との間で日華平和条約を締結した。しかし、その後、中華人民共和国を承認し、中華民国を未承認としたので、中国との関係で、日華平和条約における請求権放棄条項の扱いが問題となる。後述する西松建設事件最高裁判決は、日華平和条約と日中共同声明がいずれも「サンフランシスコ平和条約の枠組み」の下に締結されたものであるとして、日中共同声明の曖昧な表現に、日華平和条約と同様の意味内容を読み込み、更に、日中平和友好条約を介して日中共同声明が条約としての法規範性を獲得した、としている。
2.西松建設事件-中国
(1)事実関係
終戦直後に日本政府により作成された「華人労務者就労事情調査報告書」は、太平洋戦争中に徴用され、日本で働いていた中国人労働者に関するものであるが、間もなく焼却処分されたとされていた。この幻の報告書が、平成5年(1993年)に至り、ようやく発見された(*ⅲ)。その後、中国人の元徴用工が損害賠償を求めて訴える裁判が続いた。
西松建設事件判決は、平成19年4月27日に下された最高裁第二小法廷判決である(①事件)(*ⅳ)。同日に下された最高裁第一小法廷の判決があり(②事件)、第二小法廷判決と全く同一の理由付けに基づき、原告の請求を排斥している(*ⅴ)。
①判決の結論は、原審である高等裁判所の判決が事実として確定した強制連行及び強制労働を前提とする。この判決によって強制連行及び強制労働とされるのは、次の事実関係である。
「19年3月から20年5月までの間に、161集団3万7524人の中国人労働者が日本内地に移入された。なお、中国人労働者を受け入れた全事業場を通じて、総数3万8935人のうち、終戦によって中国に送還されるまでに、その17.5%に当たる6830人が死亡した」。①事件の被告である西松建設(当時、西松組)は、中国大陸に進出する日本軍の軍事行動に追随し、鉄道建設、道路工事等を受注していた土木建設会社である。①事件の原告は、広島県における発電所の建設工事のために、西松建設が中国人労働者360人の割当てを受けたうちの5名である。
この事件の被害者らは、移入当時、16才から23才までの若者であった。「家族らと日常生活を送っていたところを、仕事を世話してやるなどとだまされたり、突然強制的にトラックに乗せられたりして収容所に連行され、あるいは日本軍の捕虜となった後収容所に収容されるなどした後、・・日本内地に移入させられ」たのであり、その後、日本の警察などの監視の下で、過酷な労働に従事させられ、重大な傷害を負い、又は死亡した。西松建設に対して、損害賠償を求めていた。
②事件の被害者は、中国山西省で生まれ育った二人の中国人女性である。現地において、日本軍らによって連行、監禁され、被害者らは繰り返し、強姦、輪姦の被害を受けた。当時、13才及び15才で、未婚であり、性交渉の経験がなく、初潮も迎えていなかった。その後、重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状が存在する。日本国に対して損害賠償等を求めていた。
(2)サンフランシスコ平和条約14条(b)と19条にいう、請求権放棄の意味
最高裁判決は、サンフランシスコ平和条約が、各連合国との間で個別に行う日本国の戦後処理の枠組みを定めるものであるとする。同条約は、上に述べたように日本の賠償能力を考慮した、一括処理方式によるのである。判決は、戦争賠償と請求権を区別している。戦争賠償とは、敗戦国が戦勝国に提供する講和の条件としての金銭等のことであり、請求権とは、戦争の遂行中に生じた交戦国相互間ないしその国民相互間の請求権である。①事件、②事件で問題となるのが、請求権である。戦争遂行中に、軍隊・軍属などによる不法行為に基づく債権を生じることも多いであろう。国際法に違反するような態様による民間人に対する無差別攻撃や捕虜の虐待などの場合である。そして、戦争に勝利した国であれ、敗戦した国であれ、これらの終戦後の清算の問題が、当事国において、国及び国民・企業との相互間に生じ得るのである。
そして、判決は、個人の請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄することを定めたのがサンフランシスコ平和条約の枠組みであるとする。そして、サンフランシスコ平和条約は連合国48カ国との間で締結されたものであるが、条約の当事国以外の国・地域との間での戦後処理に当たっても、その枠組みとなるべきものであったという。
判決によると、請求権処理の問題を、個人の請求権を含めて一括処理する理由は次の通りである。平和条約を締結しておきながら、種々の請求権を、「事後的個別的な民事裁判によって解決するというのでは、将来、どちらの国家又は国民に対しても、平和条約締結時には予測困難な過大な負担を負わせ、混乱を生じさせることとな」るからである。確かに、関係するすべての国及び国民・企業の、戦争遂行中における債権関係を、後に、個々の債権関係ごとに、関係国における民事裁判の方法によって解決するというのは、極めて煩雑である。そこで、その時点では不明確なものを含めて、何らかの方法で一括清算することは合理的である。
サンフランシスコ平和条約締結後、締約国であった連合国及びそれ以外の国地域との間で、戦争賠償及び請求権の処理に関する多くの条約が締結された。判決によると、その全てが、サンフランシスコ平和条約の枠組みに従う。仮に、個人の請求権に基づく裁判が可能であるとすると、それらの多くの諸国の国民と、わが国ないし企業等との間での訴訟が続発する可能性もあり、まさにパンドラの箱を開けるといことに成りかねない恐れがある。
国家にはその国民のために、相手国に対して、国民の有する請求権を行使するという外交保護権が、国家固有の権利として存在する。サンフランシスコ平和条約にいう「請求権の放棄」とは、外交保護権の放棄に止まらず、個人の請求権を含めて相互にこれを放棄することであると、判決は解している。そして、国家は対人主権に基づき、国民固有の権利である私権を国家間の合意によって制限することも可能であるとしている。
ただし、請求権の放棄の趣旨が、事後的個別的な民事上の請求に委ねることの複雑さと困難を避けるということであるから、実体権を消滅させることまでを意味するのではなく、「裁判上訴求する権能を失わせるにとどまる」とする。
実体権はあるのに、裁判上訴求する権能がないということは、法律の専門家以外には理解が困難であろう。しかし、これはこの判決に特異な新奇の概念ではない。いわゆる自然債務というものである。民法の教科書でよく例にされるのが、公序良俗に反するある種の契約上の債務である。当該契約は無効であるから、その対価を支払う法的義務はないが、その対価を自発的に支払うとすると、相手方がそれを受領しておける権利は存在するのである。判例もある。
上記最高裁判決でも、戦争遂行中に生じた請求権について、「その内容にかんがみ、債務者側において、任意の自発的な対応をすることは妨げられない」としている。
なお、判決は傍論において、次の二点を特に指摘している。西松建設が強制労働により相応の利益を得ている。終戦後、わが国で中国人労働者を受け入れた土木建設業者の団体が、中国人労働者を受け入れたことに伴って諸々の損害が生じたと主張して、国に陳情を繰り返したので、昭和21年に国がそのための補償を与えていた。西松建設も、当時の金銭の価値からすれば極めて多額な92万円余りの補償金を取得した。そこで、「西松建設を含む関係者において、被害救済に向けた努力をすることが期待される」(下線は筆者)。
①事件は、西松建設が勝訴したのであるが、判決後に訴訟外の和解が成立した。西松建設が強制労働について謝罪し、中国人労働者360人を対象として、2億5000万円を信託して補償などのための基金を設けるという内容であった(*ⅵ)。
上に述べたように、サンフランシスコ平和条約19条は、日本国及び日本国民が連合国及び連合国国民に対して有する請求権の放棄を規定している。最高裁平成9年3月13日判決(*ⅶ)が、日ソ共同宣言に基づくわが国民の請求権放棄について次のように言及している。わが国の国民がシベリア抑留者として強制労働に従事させられたことに基づく損害賠償請求に関して、わが国が、ソビエト連邦に対する外交保護権を放棄した結果として、被害者個人がソビエト連邦に対して「賠償を求めることが実際上不可能となった」とする。わが国の政府、及び最高裁の立場が、日本国民の有する請求権の放棄とは、外交保護権の放棄を意味し、実体権が消滅するのではないとしてきたのであり、西松建設最高裁判決とも整合的である。
3.日韓請求権協定
サンフランシスコ平和条約4条にいう、日本と韓国との間の特別取極めが、1965年に締結された日韓請求権協定である(*ⅷ)。条約の解釈は、その文言の通常の用法に従い、当事国の関係合意等、及び起草文書や準備作業によって確定される(条約法条約31条、32条参照)。日韓請求権協定2条に基づき、日本及び韓国は、①領域内に存在する相手国、国民の「財産、権利及び利益」と、②日本及び韓国、及びその国民相互の間の「請求権」に関する問題が、完全かつ最終的に解決されることを確認し、何らの主張もすることができないものとする。そして、日韓請求権協定について合意された議事録によると、①の「財産、権利及び利益」、及び②の「請求権」として、包括的に財産的問題の解決がなされるのであり、韓国により提出された対日請求8項目の範囲に属する全ての請求を含む。
これを受けてわが国の、日韓請求権協定第2条の実施に関する措置法(*ⅸ)は、上記①にいう「財産、権利及び利益」に該当する実体権が昭和40年6月22日に消滅した旨規定した。この意味であるが、「法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利」をいうのであり(合意議事録)、「日韓請求権協定の署名の日である昭和40年6月22日当時、日韓両国において、事実関係を立証することが容易であり、その事実関係に基づく法律関係が明らかであると判断し得るものとされた債権」を意味するとする判決がある(*ⅹ)。
上記②の請求権については、日韓請求権「協定の締結に際して、韓国側が資料によって法律関係を明確にすることの困難なもの」で、「協定の締結当時に具体的な問題として取り上げられていなかった請求権」を含むとしている。わが国の行政解釈も、法律的根拠の有無自体が問題になっているというクレームを提起する地位を意味するとしている(*ⅹⅰ)。そして、それが昭和40年6月22日以前に生じた事由に基づくものであれば、いかなる主張もすることができないものとされた(*ⅹⅱ)。
日韓請求権協定2条にいう「請求権の主張ができない」ことの意味について、西松建設最高裁判決後において、日韓請求権協定も「サンフランシスコ平和条約の枠組み」の下に締結されたのであるとして、同条約の請求権放棄と同様の意味に解する下級審判例が続いている。(*ⅹⅲ)すなわち、実体権として消滅するということはないが、裁判上訴求することができないものとされている。
それ以前の韓国元徴用工裁判例においても原告の請求が認められていなかった(*ⅹⅳ)。但し、理由付けが異なっていたので、西松建設最高裁判決が転機となっている。
日韓両政府が、日韓請求権協定締結の際に合意した議事録によると、上に言及した対日請求8項目の中には、元徴用工の未払い賃金及び補償が入っており、これらを含めて最終的な解決を行ったのである。そして、日韓請求権協定を受けた韓国内の措置として、次の様な法律が制定された。すなわち、協定1条に基づき、日本から供与ないし貸与される資金で、1945年(昭和20年)8月15日以前までの日本に対する民間請求権が補償されなければならないとする。このような韓国の立法措置は、日韓請求権協定の解釈としての韓国の事後的な国家実行を示している。この韓国の解釈が変更されたのである(*ⅹⅴ)。
4.小括
人類が二度にわたる世界規模の戦争を経験した。戦勝国のみが一方的に敗戦国に賠償を求めれば足りるとすることの失敗が、再度の戦禍を招いたのである。戦勝国であれ、敗戦国であれ、その国の国民は共に戦争犠牲者である。戦争遂行中の被害に対しては、いずれにせよ賠償を求める権利はあっても良いはずである。敗戦国ないしその国民にも、戦争に基づく一定の請求権は存在することを、サンフランシスコ平和条約が前提している。戦争を始めた国が戦争賠償を行う義務を有することを確認しつつ、しかし、直ちに完全な賠償を行わせると、国の経済が持続不可能となる。そこで、当事国相互の間で、個人請求権を含めて、債権債務の関係を一括清算したものと考えられる。戦争によって、焼け野原となった国土と枯渇した国家財政や資源を前提として、戦勝国である債権国団との間で、債務国たる敗戦国の、いわば国家破産の処理を行う仕組みを整えた。そのおかげで、戦後、日本は、再度の経済発展が可能となり、世界経済全体の発展の一翼を良く担うとともに、あるいはけん引しつつ、世界平和に貢献できる国家となって再出発したのである。
日本と韓国の終戦に伴う財産的処理をまとめる。まず、日本が朝鮮半島に残した鉄道などのインフラその他の施設、日本の国民・企業の財産については、サンフランシスコ平和条約4条(b)に基づき、アメリカを介して韓国に委譲された。日韓請求権協定1条に基づき、日本が韓国に3億ドルの無償供与、2億ドルの長期低利貸与を行う。そして、日本及び韓国、及び各々の国民の、財産、権利及び利益、及び全ての請求権について、相互にいかなる主張もできないものとして、「完全かつ最終的に解決された」(2条)。
わが国の行政府及び裁判所の解釈によると、日韓請求権協定にいう請求権というのは、協定締結のときには、原告の範囲も、その実体も未確定な権利である。戦争に伴い発生し得る財産的権利を包括し、後に事実関係が判明するようなものを含む。元徴用工の強制労働に対する、不法行為ないし契約上の損害賠償請求権がこれに該当する。日韓請求権協定は、戦争中に生じた事実関係の下で、将来発生し得る債権を含めて、日本と韓国が包括的にいわば和解したということになる。
しかし、韓国の解釈がこれと対立している。次回は、日韓請求権協定と、日本及び韓国の解釈が対立していることの意味を、国際法と国内法の関係の観点から考察したい。
注
*ⅰ) 岩月直樹「日本に求められる「戦後補償」とは?-「慰安婦」問題における「法的責任」をめぐる難しさ」『国際法で世界が分かる[ニュースを読み解く32講]』322頁、328頁。
*ⅱ) 但し、4条(b)後述。
*ⅲ)NHKのドキュメンタリー番組で報道された。現在、外務省外交史料館に写しが保存されている。
*ⅳ) 判タ1240号121頁など。
*ⅴ) 前掲
*ⅵ) 毎日新聞記事2009年10月23日付け
*ⅶ) 判タ949号70頁
*ⅷ) 日韓請求権協定について、萬歳寛之「日韓請求権協定と韓国徴用工判決」論究ジュリスト30号(2019)67頁以下。
*ⅸ) 法律第144号(昭40・12・17)
*ⅹ) 名古屋地裁平成17年2月24日判決・判タ1210号186頁
*ⅹⅰ) 前掲萬歳69頁、名古屋地裁平成17年2月24日判決解説(訟月52巻9号1頁)参照。
*ⅹⅱ) 前掲名古屋地裁判決
*ⅹⅲ) 名古屋高裁平成19年5月31日判決、名古屋高裁金沢支部平成22年3月8日判決、富山地裁平成19年9月19日判決。なお、名古屋地裁平成17年2月24日判決は、最高裁判決以前のものであるが、この系譜に属する。
*ⅹⅳ) 東京高裁平成14年3月28日判決(訟月49巻12号3041頁)、東京地裁平成8年11月22日判決(訟月44巻4号1頁)。わが国の国内法上、国家無答責の法理が適用される、契約債務としての安全配慮義務違反とならないとする、また、国際法の直接適用に基づく損害賠償が否定される。消滅時効や除斥期間も理由として考えられる。
*ⅹⅴ) 岩月・前掲330頁参照。