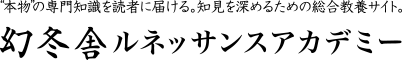連載
一覧夏目漱石の予言 【第2回】―文芸上の真 ―

半藤 英明(はんどう ひであき) 熊本県立大学 学長
人には生きる上で強い者もいるが、大抵は弱いのではないか。「弱い」とは体力、気力の話ではなく、悩み、傷つき、我慢して生きているという意味である。だから、何かを期待し、何かを当てにし、何かに依存する。誰しも愛し愛されたいし、救われたい。趣味や生き甲斐を求めるのも文芸や宗教の存在も、その証しであると思う。
幼少期はいさ知らず、大人の漱石は生真面目で思索的な学者肌である。生きることに過度に真剣で、陰鬱な不安感に苛まれていた。それを脱し、安心して生きる手掛かりとしたのは、「自己本位」による文芸の建設を人生の営みと思い定めたことである。小説の動機は、生きることの不安を解消するための無限の追求であった。小説を一度も停滞せずに済んだのは、そのためでもある。
漱石は、松山、熊本での英語教師を経て、文部省の薦めによるロンドン留学後に東京帝国大学の講師となり、英文学の講義を行った。それを纏めた明治40年の『文学論』は、心理学、社会学を応用した専門的でペダンティックな文章の学術書であるが、そこに漱石の基幹的な作家態度が見える。例えば「文学者の重(おもん)ずべきは文芸上の真にして科学上の真にあらず」と述べては文学と呼ぶべきものが文芸上の真すなわち創作上のリアルによって読者の心に訴えかける行為であると宣言している。本当らしい出来事を描いて大方の想像力に働きかけるものが文学であるという。表現上の世界にこそ大切な真理が浮遊する場合もあるだろう。人は自分で選んだ単線的な現実しか送れないが、文芸の世界で異なる人生を追体験するならば人生の理解を広げたり深めたりすることができる。疑似体験の全てが実体験に劣るとは誰も言い切れまい。現実ではあり得ないことを、文学という名の文芸上で実現し、現実相当の世界を表現したり理解したりすることは十分あり得る。「事実は小説より奇なり」と言うが、事実が常に小説を超えるものであるならば小説の敗北であり、小説にはたいした価値がないことを意味する。