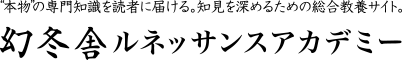連載
一覧「箸文化」の「中庸」という人間関係のバランス感覚【第4回】

馬 彪 山口大学大学院東アジア研究科教授
トインビー氏が中国について「独特の思考法を二千年余にわたってつちかってきた中国民族です」(A.J.トインビー・池田大作『二十一世纪への対話 下』)といったことがあるが、その「独特の思考法」とは一体なにかという課題がのこされた。本論にしたがって言えば、「箸文化」の「中庸」という人間関係のバランス感覚こそ、その「独特の思考法」のあたるのだろうか。
西洋文化が激烈的な個人主義を強調するのとはちがい、中国人は「中庸」という調和的な人間関係を重視する。それは孔子が提出した独特な「中庸」という概念であるが、しかし孔子はこの概念を提出した根拠は『易』にあるらしい。なぜならば『易』(英文訳はBook of Changes)に八掛における下卦の中位に居る「二爻」と上卦の中位に居る「五爻」によって「中道」を表わして、つまりすべてのChangesは、つねに「中位」を前提として動いたのが重要だと考えられた。
「中庸」とは人と人の間の調和的な関係を重視すること、いわゆるどちらにも片寄らない中ほどのことである。不偏不倚で過不及のないこと。中正の道。つまり、バランスをとることはなにより大切なことだと強調する思想である。
その意はまた三つにわけられるはずである。第一意は、「中」は片寄らず、「庸」は易(かわ)らず意である。人間は極端にならず、自分の目標や主張は変わらず。これが成功する正しい道であるという。第二意は、「中正」「平和」の意である。人はつねに「中正」「平和」の心を持ち、それらをうしなったら喜・怒・哀・楽のバランスが崩れ、人の健康に悪い。第三意は、「中」は好しいの意であり、「庸」は「用」と同じである、即ち用にあたる意で、役に立つという意味である。
一説には、中国人の「中庸」思想は、ギリシャのアリストテレスの徳論の中心概念と似ているといえる。それは、過大と過小との両極の正しい中間を知見によって定めることで、その結果、徳として卓越する。例えば、勇気は怯懦と粗暴との中間であり、かつ質的に異なった徳の次元に達する。『論語』「雍也」に「中庸こそは完全至高の徳だ(中庸为德也、其至矣乎)」とある。何晏の『集注』には「中は、過無く不及無きの名なり。庸は、平常なり」(中者、無過無不及之名也。庸、平常也)とある。程頤の注には「偏せざるを之れ中と謂い、かわらざるを之れ庸と謂う(不偏之謂中、不易之謂庸)」とある。
中庸思想によっての「不卑不亢」(卑屈でもなく傲慢でもない)という対人態度は、いにしえから最も適当的な人間関係をとれるマナーだと考えられてきた。なぜなら、そのような対人意識があれば、個人と共同体との統一や国と国との外交関係もスムーズに果たせるからである。
中庸思想に基づけば、国家、とくに漢帝国における儒教国家の人間管理でも、皇帝の君主専制を実行すると同時に、官僚の選挙制を行っている。法律国家機能を厳密に備える(近年、出土した秦漢時代の木簡・竹簡の過半数は当時の法律文書)一方で、「孝」を中心としての倫理教育の推奨に力を尽くす。いわゆる朝廷の「内法(法律)-外儒(倫理)」政策である。
国家の運営について、歴代の中で難しい問題の1つは、皇帝の君主権と家族長の宗族権とのギャップである。それは、いわゆる「君統-宗統」の間にいかなるバランスをとるかということである。現代語に換言すれば、民主と君主と統一するかどうかの難問題である。
ヨーロッパの小さい各邦国とはちがい、中華帝国はつねに莫大な領土を持ち、巨大な国家機構を運営しなければならない。したがって、知識人はいにしえから官僚との協力を求められてきた。古代ギリシャの哲人は官僚になりたくないと考えていたが、中国では知識人と官僚の性格を併せ持つ士大夫が2000年前にも政治舞台に登場した。このことはまさに知識と行政管理とのバランスをとった所産である。士大夫という概念でさえ西洋には存在しなかったため、どのようにその言葉を西文に訳すかの問題は、近世において中国を訪ねた欧州宣教師の頭を非常に悩ませたのだろう。結局はscholar-bureaucratやscholar-officialsとのような合成語にしか訳すことができなかった。
国際関係にも中庸思想は通用する。西洋の「国家利益主義」と違い利益より正義を重視することは、国際外交においては原則である。つまり、外交信用を失なくないためには、利益のための武力や経済力の侵入はみとめられないのである。
戦争において、西洋人はまた勝利者が英雄と考える(スーパーマンとは英雄を象徴する)が、中国では「先礼後兵」や兵器=凶器や「武帝」という諡号は、マイナスの意味もある。戦争はみな人間関係を崩すこととしてみとめられないのである。
スポーツでいうと、古代からギリシャの五輪精神は「より強い、より高い、より速い」というよく耳にしているスローガンがあるが、いにしえから中国人のスポーツ観はそれとはちがい、むしろ「よりバランスをとる」ことであった。つまり動と静、身と心(わざ)の平衡性を大切にし、激しくせずとも健康維持や生命力をアップすることを目標とする。例えば、武術家出身の俳優のブルース・リーやジャッキー・チェンのカンフー・アクション映画の世界で、有名になった中国武術(カンフーともいう)の基本原則は勝負より武徳だ。武徳とは武術家として守るべき徳義である。
「中庸」感覚によって最も典型的な中国式な精神現象は、本土の儒教や道教を外来の仏教と融合的に受け取った、いわゆる「三教合一」である。西洋人のキリスト教は他の宗教と融合しないやり方と違い、中国本土の儒教や道教などは、むしろ中庸的な姿勢で、輸入してきた仏教を包有・補完してきて、特に統一した時代には「三教合一」という主張に注目するべきだ。
例えば、約300年の南北朝の分裂を終らせた隋王朝には、儒学者の文中子(王通)が儒教の「中道」論を中心として儒・釈・道という三教の矛盾点を調和しての「三教可一」説を提出した。唐時代における朝廷の仏教・道教とも推奨した結果は、釈教・道教も儒教と同じく発達して、儒教も積極的に釈教・道教を受け入れた。ついに宋・明時代の新儒学が誕生し、儒教を中心としての「三教合一」説は盛んになった。
一方、明代になると民間には儒教の説教を重んずる「三教合一」の形式をした民間宗教は庶民たちの関心を惹いた。今日に至っての中国には日本のお寺と神社のような仏教寺院と道観があるが、別に「三教合一」の寺廟もある。例えば、有名な山西省の懸空寺や寧夏回族自治区の高廟などはみなこの類いのお寺である。
最後に、いわゆる中国文化の「十六字真言」を説明しながら、今回の話を終わりたいと思う。それは『尚書』「大禹謨」に「人心惟危、道心惟微、惟精惟一、允執厥中」とある名言である。やや難しそうな言葉だが、これは中国の古の聖人の舜は天子としての心得であり、意味は人間の心は不善におちいりやすく、危険なものである。道義におもむく道心はかすかにして明らかなり難しいものである。常に私心をまじることなく、終始ただ道心の命に従ってこれを守り、過不及なく、中道にあわせなければならないことである。つまり、国家を管理する要領である。
ここでいう「道心」の「道」は仏陀の道、仙人の道、孔子の道とさまざまな解釈はできるが、最も重要なのは文末の「中道にあわせなければならない」という古訓の「中」であろうか。なぜならば、この文こそ4500年の間にわたってきた中国文化の精髄になったものだといえよう。実は、その「允執厥中」とはまさにここで述べた箸文化によって出てくる「中庸」という人間関係のバランス感覚よりほかないだろうか。
引用文献・参考文献
◆『尚書』『周易』『論語』『孫子兵法』『中庸』『中説』
◆A.J.トインビー・池田大作『二十一世纪への対話』下、文藝春秋1975年
◆常盤大定『支那に於ける佛教と儒教道教』東洋文庫論叢,1930年