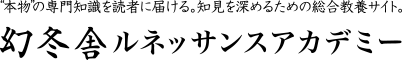連載
一覧「美しい国」の構造分析【第5回】―日本農村社会学再考―

中筋 直哉 (なかすじ なおや) 法政大学社会学部教授 地域社会学・都市社会学専攻
日本の社会学のなかでも独特の消長を見せた日本農村社会学の魅力を省みながら、現在の中山間地域問題、コミュニティ問題への応用可能性を探る。
最5回:日本農村社会学のフィールド その2―熊本県あさぎり町須恵
次に取り上げる日本農村社会学のフィールドは鈴木栄太郎のものであるべきだが、実は鈴木にははっきり跡づけられるフィールドがない。しばしば言及される北海道美深町恩根内(おんねない)や秋田県西目屋村大秋(たいあき)は、戦後の著作『都市社会学原理』(1957)の論拠で、かつ助手に調査させたものである。
そこで鈴木のアドバイスを受け、またその成果を鈴木が絶賛した研究のフィールドを訪ねてみよう。それはJ.F.エンブリー(1908-1950)『日本の村 須恵村』のフィールド、熊本県あさぎり町須恵である。エンブリーが須恵を訪れたのは、有賀が石神を訪れたのと同じ1935年だった。
エンブリーはアメリカ人で、シカゴ大学でA.ラドクリフ=ブラウン(1881-1955)のもとで社会人類学の博士号を得た後、ユカタン半島の近代化を研究したR.レッドフィールド(1897-1950)やオーストラリア原住民の親族構造を研究したW.L.ウォーナー(1898-1970)ら先輩に倣って日本でのフィールドワークを志し、亡命ロシア人で、日本で育った妻と幼い娘を連れて日本にやってきた。彼は着いてすぐに柳田や鈴木を訪ね、フィールド選定について教えを請うた。
須恵を選んだのにとくに積極的な理由はなく、特殊な偏りがないことが大きかった。だから研究も、有賀の描き出したオーヤ斎藤家のような極端な事実を描き出すのではなく、小さな村の日常と四季を淡々と描き出した。また、ラドクリフ=ブラウン仕込みの親族組織分析のかわりに、「オンナ・コドモ」の生活世界を、夫人の協力によってていねいに描き出した。
1年間の滞在後帰国したエンブリーは、1939年『日本の村 須恵村』を出版した。それに対して、鈴木は直ちに好意的な書評を与えた(1940)。この本に不朽の価値を与えたのは、外国人が書いた『美しい国』の分析としてもっとも有名な作品、R.ベネディクトの『菊と刀』(1946)が論拠に用いたことである。日本を訪れたことのないベネディクトにとって、同じ文化人類学者の手になる本書は非常に有用な参考書だった。もっとも当のエンブリーは、アメリカの日本占領には関わっていない。
石神訪問が軌道に乗り始めた頃、私は、次は須恵を訪れたいと思った。幸い研究費を得られ、5年間毎春須恵に通った。ただ斎藤方男さんとのすれ違いに傷ついた私は、エンブリー夫妻の昔話をしてくれる老人を探す気になれなかった。そのうえ、私の話し方がまずかったのか、地元の人びとは、エンブリーのことを誇りには思っているが、今それほど興味があるわけではない、という感じだった。福武とその弟子たちが研究した通り、石神も須恵も、20世紀後半の農業改善と地域開発の影響をもろに受けて大きく変貌していたし、さらにどちらの村も「平成の大合併」の只中にあった。私も、元々の懐旧的関心は薄れ、現代的な研究をものしたいという野心ばかりが空回りした。
私が定宿にしたのは隣村(今は同じ町内)のトマト農家で、中世相良領の城館そのままの屋敷地に建つ旧家だった。おそらく石神の斎藤家より古いだろう。しかし私は有賀のように、その家の系譜をていねいにたどることをせず、イグサからメロン、メロンからトマトといった、企業農としての経営展開の話ばかり聞いていた。もっとも当主は、方男さんと同じく礼儀正しく親切で、これぞ旧家の主という感じの方だった。だからといって八幡平の人びとが斎藤家さんに抱いていた距離感は、ここにはないようだった。
エンブリー時代の須恵は球磨川の氾濫に悩まされていたが、それは市房ダムによって解消し、さらに山側の集落には用水が引かれて良質の茶畑が開かれることとなった。おそらくこの成功体験が、私が訪れていた頃この地域最大の政治問題となっていた「川辺川ダム」問題につながったのだろう。
エンブリーの一番の協力者は、村の焼酎蔵元の跡取りの青年だった。しかし彼はエンブリーが去った後すぐ、当時は珍しい自動車事故で亡くなってしまう。彼の家「六調子」は、今は隣町で営業を続けている。私はそのかわりに、これも隣村(今は同じ町内)の焼酎蔵「松の泉」の食堂で昼を食べることを調査中の習慣にしていた。
もう1つ須恵が石神と大きく異なるのは、石神は盛岡の城下まで遠く、影響も限られるのに対して、須恵は人吉の城下に近く、影響が大きいという点だ。ただしその影響は好いものばかりではなく、たとえば「昔は買い物に行くと田舎者と馬鹿にされた。だから人吉の商店街で買うより隣町のスーパーで買う」といった声も聞かれた。そのせいか、旧相良領、人吉盆地一帯で広域合併することは不可能なようだった。こうした村を超える市場交流と政治について、エンブリーは多くを記していない。こうした社会を閉鎖的にみる偏見は、やがて鈴木が気づき、乗り越えていく点であり、日本農村社会学の欠点でもあった。