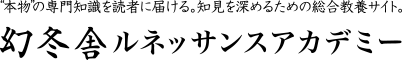連載
一覧「美しい国」の構造分析【最終回】―日本農村社会学再考―

中筋 直哉 (なかすじ なおや) 法政大学社会学部教授 地域社会学・都市社会学専攻
最終回:「美しい国」の構造分析―日本農村社会学の活かし方
これまで5回にわたって日本農村社会学を紹介してきた。最終回では、もともとの問題関心に戻って、この「美しい国」の可能性と課題を考えるために、日本農村社会学をどのように活かすべきなのか、もう少し論じてみたい。
日本農村社会学に対して、現代の社会学者のなかでもっとも根底的な批判を加えたのは、ジェンダー研究者の千田有紀である(『日本型近代家族』,2011)。千田は、第二次世界大戦後の日本において近代主義的な家族社会学が成立する際、その敵手として構築されたのが日本農村社会学であるという。近代主義的な家族社会学が行き詰まった今、この批判は適切で、建設的だと思う。しかし千田も気づいているように、もともとの鈴木や有賀の実感や直観のリアリティは、そうした批判では解消できない確かさを持っていたし、そもそも日本農村社会学は家族社会学ではなく、地域社会や国民文化の理論だったのだ。千田の議論を踏まえて言うなら、まさにポストモダンな現代だからこそ、主流派の近代主義が否定した、もうひとつの近代主義的学問運動である、日本農村社会学のリアリティを見直す余地があるのではないだろうか。
では、私たちは日本農村社会学をどう見直し、活かせばいいのだろうか。
まずその理論モデルに磨き直して、「美しい国」の分析に適用してみる可能性があるだろう。日本農村社会学はかつて、「第二の村」(神島二郎)とか日本的経営といった、近代化していく社会に残る「遺制」のモデルを提供したし、また「ジャパン・アズ・ナンバーワン」(E.ヴォーゲル)の時代には、「競争的集団主義」(村上泰亮)のモデルを提供した。それらはいずれも、市場取引関係が全面化し、「相克的」(真木悠介=見田宗介)に生きる他なくなった私たちが、にもかかわらず、肯定的な意味で集団主義的であることを説明するために用いられたのである。
しかし今、私たちは相変わらず肯定的な意味で集団主義的であることを望む一方(コミュニティ願望)、否定的な意味の集団主義に苦しんでいる(いじめ、いじり、空気、忖度)。こうした集団主義のジレンマを乗り越えるために、鈴木や有賀の理論モデルを再利用することができるのではないだろうか。
つぎに福武のいう「構造分析」にも再利用の可能性が残されているだろう。福武は一般的には戦後の近代主義者の一人と見なされてきたが、他の近代主義者とちがう個性を持っていて、それこそこの「構造分析」なのである。それは構造を批判するだけではなく、構造の内発的発展力にも注目し、かつ外挿的に構造に介入する政策を構想する。福武にとって構造とは村や家だったが、現代の私たちは、性別役割分業の残存とか労働のブラック化といった「昭和の体制」を構造と見なして分析し、政策によって改革していくことができるのではないだろうか。
第三に日本農村社会学が、当時世界標準の社会学を用い、国際比較の視点を立っていたことを再評価すべきだろう。「だから日本、スゴい」ではなく、フラットな目線での比較社会学の可能性が今も開けているのだ。たとえば文化人類学者E.トッドの議論に参戦する武器になるのではないだろうか。
第四に日本農村社会学の「外部」を逆照射することができるだろう。それは農村の現場に固執した結果、農村ではない社会や農民から疎遠な生活から目をそらしていたのではないだろうか。逆にそこを見つめ直すことによって、より多様な日本社会像、日本史像を描き出せるのではないだろうか。
私は都市社会学者なので、とくに2つの外部すなわち都市と移民が気になる。都市は多くの場合住民の定着を許さず(その極限的事例がホームレス)、また都市騒乱事件など、一時的かつ流動的な社会現象が社会全体に大きなインパクトを与えることがある(拙著『群衆の居場所』,2005)。だから私は都市を、文化人類学者P.クラストルに倣って「共同体と歴史に抗する社会」と呼びたい。
また移民については、たとえば沖縄出身で戦間期に南洋群島に渡り、玉砕戦を生き延びたが、戦後米軍基地に占拠された沖縄に戻る土地はなく、さらに南米に移民して苦心惨憺、今は子孫が中部地方の自動車工場で働いている。しかし沖縄の本家にある先祖の位牌はまだ心の拠り所であり続けている、といった事例は、日本農村社会学ではけっして分析することができない。
終わりにひと言。私は福武直の弟子の弟子、つまり福武は学問的祖父にあたる。鈴木や有賀に会ったことはなく、福武との最初の「出合い」も彼の葬式の手伝いだったから、学派の「家」的な統制力は大きいとは言えない。ただし、若い頃はまだ日本農村社会学の現役世代からの「村」的統制力を感じることが多かった。今はこの「家」も「村」もほぼ滅びてしまった。だから、これからの社会学者たちは、まったく自由にこのユニークな知識にアクセスし、活用することができる。日本農村社会学が書庫の一隅に埋もれることなく、新しく有用な知識の源泉になっていくことを願ってやまない。