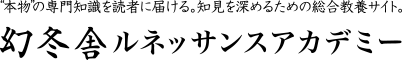連載
一覧気象津波 ~気象現象によって発生する潮位副振動~【第1回】 気象津波とはどのような波なのか

田中 健路(たなか けんじ) 広島工業大学 環境学部 地球環境学科
気象津波とはどのような波なのか
2019年3月21日午後8時40分頃、長崎市内の低地を流れる小川や水路,道路の側溝から次々と水が溢れだした。
「雨もほとんど降っていないのになぜ」
「水道管が破裂したのか」
「高潮??」
気象庁から潮位副振動に関する観測情報が報道されるまでの間、何が起こったか戸惑う投稿がツイッター上などで飛び交った。長崎をはじめとする九州では「あびき」と呼ばれている潮位副振動と大潮の満潮時潮位が重なったものであったのだ。
潮位副振動は、地球と太陽や月などの天体間の相対関係で引き起こされる天文潮汐の周期よりも短い、数分~3時間程度の周期を有する波の総称である。潮位副振動の発生原因は、海洋の内部波であったり、湾内での多数の船舶の航行によるものであったりと様々である。その中でも、大気側からの作用によって生じるものは、最大全振幅が1mを超え、極端な事例では3m近くの巨大な波として襲うものも見られる。そして、波の周期や伝播の特徴が、地震によって発生する津波の周期と同程度の長さであることから、「気象津波(meteorological tsunami または meteotsunami)」と呼ばれるようになってきている。本連載では、気象津波の現象について、発生の基本的な仕組みや国内外の発生事例、現象解明や予測に向けた研究の現状と課題について述べていきたい。
気象津波と地震津波、台風などによって発生する高潮との類似・相違点についてまとめたものを表-1に示す。

主な外力として、気象津波は高潮と同様に気圧の吸い上げ効果が重要な要素として寄与する。高潮と気象津波の大きな違いは、個々の波の周期・波長および大気側の外力の進行速度の2点が主として挙げられる。高潮は低気圧全体の気圧場や風速場おおび移動によって長波の移動や発達が支配されることから、地上天気図から波の特徴が概ね判別可能である。一方、気象津波に関わる気圧波は、地上天気図では識別できない波長30~200km、全振幅1.0~5.0hPa程度の規模であり、個々の気圧波が時速100kmを超える速度で海面を進む特徴を持っている。このような気圧波は、上空の大気の安定・不安定の分布によって引き起こされる重力波が海面に向かって伝わったものなどによるもので、地上天気図のみでは波の進行方向や範囲などの特徴が十分につかめない。高潮と比べて気圧変化が小さく、波長も短いのに、最終的に到達する波は高潮と同程度、あるいはそれを超える高さの波として襲うことに疑問を感じる方が多いだろう。気象津波の発達には、複数の発達メカニズムが携わっているのである。
一般的に高潮の原理で説明に用いられる気圧の吸い上げ効果は、1hPaあたり約1cmの海面昇降がもたらされる。だがこの関係は、低気圧が海上で静止していると仮定した場合のものである。気圧波が移動する際に海面で形成された波も広がっていく。海域の水深に対して波長が十分に長い海洋長波は、気圧波の位相速度と海洋長波の位相速度がほぼ等しい条件下では、気圧差によって海面に加えれた力が進行中の海洋長波に加わり続け、波にエネルギーが蓄積され、徐々に波高が増大する。海洋長波の一つである気象津波はこの効果により、大陸棚および大陸棚斜面を進みながら増幅する性質を持つ。
一方、高潮は低気圧の移動速度が遅く洋上での増幅は殆ど生じない。洋上で徐々に増幅した気象津波は、浅瀬に近づくと地震津波と同様に波高が増大し、気象津波の周期と港湾の固有振動周期が重なると、湾内で更に共鳴が起こり、振幅が増大する。湾奥に向かって幅が徐々に細くなる遠浅のV字状の形状の湾の場合、概ね湾幅の2分の1乗、水深の4分の1乗に反比例して波高が高くなる(Greenの法則)。また、浅海域で反射した波が、水深が急に深くなる大陸棚斜面で反射あるいは全反射し、再び岸側に戻る際に増幅する効果も生じることがある。以上の増幅および共鳴効果により、最終的に初期状態から数10倍~100倍以上に波高が増大するのである。
これまで、気象津波とはどのような波か述べてきたが、その原理に関する研究は20世紀前半には既に行われてきていた。1929年にProudmanによって気圧波と海洋長波の移動による共鳴効果に関する理論の基礎を構築し、1935年に京都帝国大学の野満隆治教授が大気側の外力で励起される津波に関して、風や気圧変化によって波高が増幅するメカニズムについて論じた。気圧波に関しては、Pressure jumpと呼ばれる突発的な気圧変動や低気圧、前線など様々な天気条件の下で観測されていることが20世紀の半ばにレビューされていた。計算機の発達と共に、海洋上の長波の伝播過程のシミュレーション研究が可能となり、洋上で発生した気圧波により、共鳴・増幅を重ね、数10倍に増幅する一連の過程を統合的に解明することが可能となった。
その代表的な例が、1982年に発表された日比谷・梶浦による1979年3月31日に長崎湾で最大全振幅278cmを記録した事例を基に解析した論文である。1980年代以降、気象・海洋それぞれの分野で全球規模の観測プロジェクトを機に、大気海洋相互作用に関する研究が活発に行われるようになり、気象学・海洋学双方の観点から気象津波に関する研究が進められ、かつて予測は不可能に近いと言われていた現象が、数日前からの予測の可能性の扉が開きつつある段階に来ている。
以降、本連載では、第2回目・第3回目にそれぞれ、日本国内の発生事例、海外の発生事例についてレビューし、第4回目に気象津波を発生させる気象場について最近の研究で明らかになったことについて述べる。第5回目に予測や早期検知に向けた技術開発の現状と課題について述べる。
参考文献
Defant A.: Physical Oceanography, vol. II, Pergamon Press (1961)
Hibiya T. and Kajiura, K.: Origin of the Abiki phenomenon (a kind of seiche) in Nagasaki Bay, J. Ocean. Soc. Japan, 38, 172–182, (1982)
Nomitsu, T. : A theory of tsunamis and seiches produced by wind and barometric gradient, 京都帝國大學理學部紀要,A18, No. 5. (1935)
Proudman, J. : The effects of the sea changes in atmospheric pressure, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Supplement 2, No. 5, p.197-208 (1929)
宇野木早苗:港湾のセイシュと長周期波について,海岸工学講演論文集第6巻, p.1-11 (1959)